石田 秀輝(いしだ ひでき、1953年(昭和28年)1月1日生まれ)は、東北大学大学院環境科学研究科の教授・同済大学客員教授・ものつくり生命文明機構理事・アースウォッチ・ジャパン理事・ネイチャー・テック研究会代表である。
引用
深夜ラジオで知りました・
石田 秀輝(いしだ ひでき、1953年(昭和28年)1月1日生まれ)は、東北大学大学院環境科学研究科の教授・同済大学客員教授・ものつくり生命文明機構理事・アースウォッチ・ジャパン理事・ネイチャー・テック研究会代表である。
http://ameblo.jp/emileishida/entry-11441915074.html
目次 [非表示]
1 人物
2 業績 2.1 クローズド生産システムの提唱
2.2 人と地球を考えた新しいものつくりの提唱
2.3 ネイチャー・テクノロジーの創成
2.4 バックキャスト思考によるライフスタイル研究
人物[編集]
地質・鉱物学をベースとした材料科学を専門とした研究者。1992年より「クローズド生産システム」を提唱。1997年から「人と地球を考えた新しいものつくり」を提唱している。
多くの実践経験をもとに、心豊かな暮らし方のかたちを基盤とした人と地球を考えたものつくり『自然のすごさを賢く活かす』ものつくりのパラダイムシフト(ネイチャー・テクノロジー)実現に国内外で積極的に活動している。2005年9月ネイチャー・テック研究会を発足、あたらしいものつくりの研究・啓発活動も開始した。
その基本は、厳しい地球環境制約の中でも心豊かに暮らせるライフスタイルとテクノロジーのあり方を追求するもので、社会科学や工学を横断するあたらしい概念の創出とも言える。 社会人や子供たちの環境教育にも注力している。
業績[編集]
クローズド生産システムの提唱[編集]
今後不可避とされる循環型社会とその社会における生産活動や材料開発の基本的な考え方。循環型社会におけるものつくりの概念を示し、実際のものつくり現場で展開した。
人と地球を考えた新しいものつくりの提唱[編集]
環境と経済の両立を考えるための基本的な思考で、企業は地球環境問題に正対することが不可避であるが、同時に人に豊かさを提供する義務があるという考え方。株式会社INAXにおける環境戦略の基盤となるとともに、後に展開することになるネイチャー・テクノロジー研究のきっかけとなった考え方でもある。
ネイチャー・テクノロジーの創成[編集]
持続可能な社会創成のためには、地球のことを考えたものつくり暮らし方のかたち(循環型社会)と、人のことを考えたものつくり暮らし方のかたち(生活価値の不可逆性/人の欲)を同時に肯定する必要がある。
そのため、厳しい地球環境制約の中で心豊かに暮らせるライフスタイルを描き、それに必要なテクノロジーを、完璧な循環を最も小さなエネルギーで駆動する自然の中から見つけ出し、テクノロジーとしてリ・デザインするという新しいテクノロジー創出手法である。
この手法から、水のいらない風呂、無電源エアコン、マイクロ風力発電機など新しいテクノロジーが生み出され、多くのものが実用化されはじめている。自然模倣のテクノロジーにはバイオミメティクス、バイオミミクリー等があるが、それとは別で地球環境やライフスタイルを考慮した、より大きな概念である。
バックキャスト思考によるライフスタイル研究[編集]
フォアキャストに対する考え方である。フォアキャストが現状から行動計画を立てるのに対し、バックキャストは将来から現状を考える。
将来の厳しい地球環境制約を想定し、その中で心豊かに暮らせるライフスタイルを描く。東北大学大学院環境科学研究科の古川柳蔵准教授らと、既に1500を超えるライフスタイルを描き、その社会受容性分析から、生活者が潜在的に求めている豊かさの要素を抽出している。
趣味[編集]
奄美諸島沖永良部島の自然と酒(黒糖焼酎)、そして住民に魅かれ、1997年から毎年数度通っている。2004年には、知名町のジャングルの中に別荘(屋号:酔庵)を建て、住民とのコミュニケーション、自然、料理を楽しんでいる。
紀元前後の遺跡を訪ね、昔を想い酒を飲み、機械いじり、テニスも楽しむ。
略歴[編集]
1953年 岡山県に生まれる。
1993年 名古屋工業大学にて博士(工学)取得。
1978年 伊奈製陶株式会社(現株式会社INAX) 入社
1992年 同社空間技術研究所基礎研究所(新設)所長
1998年 同社技術統括部空間デザイン研究所(新設)所長
2002年 同社取締役 技術統括部部長 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング取締役兼務
2002年 同社取締役 研究開発センターセンター長
2003年 岐阜大学工学部講師
2003年 豊橋技術科学大学工学部講師
2004年 同社取締役 研究開発センター長 環境戦略部部長 兼務
2004年6月 同社技術顧問
2004年9月 東北大学大学院環境科学研究科教授(環境創成機能素材学)
2005年 同高度環境政策・技術マネジメント人材養成ユニット(大学院コースSEMSaT)教授 研究代表 兼任
2005年 陝西科技大学客座教授 兼任
2005年 ネイチャー・テック研究会を発足
2010年4月 SEMSaTが「環境政策技術マネジメントコース」として継続決定、同コース教授 兼任
2010年7月 国際エネルギー資源戦略立する案環境リーダー育成拠点教授 兼任
2012年 同済大学客員教授 兼任
賞歴[編集]
1992年 日本鉱物学会より鉱物工学奨励賞
1993年 米国セラミックス学会よりブルナウエル賞(学術論文賞)
1994年 セメント協会よりセメント協会論文賞
1996年 米国セラミックス学会よりブルナウエル賞
1998年 簡明技術推進機構よりPort賞(機構賞)
1999年 日本ファインセラミックス協会より技術振興賞
1999年 日本鉱物学会より応用鉱物学賞
2000年 日本セラミックス協会より学術論文賞
2000年 日本セラミックス協会より学術賞
2000年 米国セラミックス学会からフェローの称号を授与
2002年 中部科学技術センターより振興賞
2002年 グッドデザイン賞[1]
2005年 自然に学ぶものつくり研究助成プログラム
2007年 第1回キッズ・デザイン賞
2007年 グッドデザイン賞[2]
2008年 東北大学大学院環境科学研究科教育賞
2010年 東北大学総長教育賞
2013年 第3回生物多様性日本アワード 優秀賞
2013年 グッドデザイン賞、グッドデザイン・BEST100賞 / 未来づくりデザイン賞[3]
著作[編集]
国内外を含め論文・総説等約400報を掲載、95の特許を取得している。
著書[編集]
自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか(化学同人、2009年1月25日、ISBN 978-4759813227)
地球が教える奇跡の技術(祥伝社、2010年3月16日、ISBN 978-4396613563)
キミが大人になる頃に。 - 環境も人も豊かにする暮らしのかたち(日刊工業新聞社、2010年9月、ISBN 978-4526065316)
Channeling the Forces of Nature(東北大学出版会、2010年10月1日、ISBN 978-4861631498)
未来の働き方をデザインしよう - 2030年のエコワークスタイルブック(日刊工業新聞社、2011年11月21日、ISBN 978-4526067822)
監修[編集]
自然にまなぶ! ネイチャー・テクノロジー: 暮らしをかえる新素材・新技術(学研パブリッシング、2011年9月9日、ISBN 978-4056064520)
「すごい自然」図鑑(PHP研究所、2011年12月8日、ISBN 978-4569782003)
ヤモリの指から不思議なテープ(アリス館、2011年12月21日、ISBN 978-4752005513)
それはエコまちがい? 震災から学んだ、2030年の心豊かな暮らしのかたち (プレスアート、2013年8月1日、ISBN 978-4990190972)
2030年のライフスタイルが教えてくれる「心豊かな」ビジネス-自然と未来に学ぶネイチャー・テクノロジー(日刊工業新聞社、2013年11月26日、ISBN 978-4526071669)
カがつくった いたくない注射針 (科学のお話 『超』能力をもつ生き物たち)(学研マーケティング、2014年2月5日、ISBN 978-4055010887)
ホタルがつくった エコライト (科学のお話 『超』能力をもつ生き物たち)(学研マーケティング、2014年2月5日、ISBN 978-4055010894)
ヤモリがつくった 超強力テープ (科学のお話 『超』能力をもつ生き物たち)(学研マーケティング、2014年2月5日、ISBN 978-4055010900)
ハスの葉がつくった よごれない服 (科学のお話 『超』能力をもつ生き物たち)(学研マーケティング、2014年2月5日、ISBN 978-4055010917)
共著[編集]
Electric Field Applications: In Chromatography, Industrial and Chemical Processes(Wiley-VCH、1995年9月25日、ISBN 978-3527286874)
水熱化学ハンドブック(技報堂出版、1997年7月、ISBN 978-4765500272)
粘土の世界(KDDクリエイティブ、1997年7月、ISBN 978-4906372386)
Materials Science of Concrete V(米国セラミックス学会、1997年10月、ISBN 978-1574980271)
Encyclopedia of Smart Materials(ワイリー・インターサイエンス、2001年12月17日、ISBN 978-0471177807)
廃棄物処理・リサイクル事典(産業調査会事典出版センター、2003年5月、ISBN 978-4882823247)
緑をまとう家 - 我流天国(INAX BOOKLET、2003年6月15日、ISBN 978-4872758245)
エコマテリアルハンドブック(丸善、2006年12月26日、ISBN 978-4621077443)
環境対応型セラミックスの技術と応用(シーエムシー出版、2007年2月、ISBN 978-4882316695)
新しいくらしかたのか・た・ち(芸立出版、2007年9月14日、ISBN 978-4874660652)
エンジニアのための工学概論 - 科学技術社会論からのアプローチ(2010年4月、ISBN 978-4623057610)
工業排水・廃材からの資源回収技術(シーエムシー出版、2010年9月、ISBN 978-4781302614)
次世代バイオミメティクス研究の最前線―生物多様性に学ぶ(シーエムシー出版、2011年9月、ISBN 978-4781304106)
survival ism - 70億人の生存意志(ダイヤモンド社、2011年11月11日、ISBN 978-4478017357)
ポスト3・11 変わる学問 気鋭大学人からの警鐘(朝日新聞出版、2012年3月16日、ISBN 978-4023310421)
自然界はテクノロジーの宝庫 ~未来の生活はネイチャー・テクノロジーにおまかせ!(技術評論社、2013年4月11日、ISBN 978-4774156538)
Nature Technology: Creating a Fresh Approach to Technology and Lifestyle(Springer、2014年1月10日、ISBN 978-4431546122)
地下資源文明から生命文明へ 人と地球を考えたあたらしいものつくりと暮らし方のか・た・ち―ネイチャー・テクノロジー (東北大学出版会、2014年2月24日、ISBN 978-4861632396)
メディア出演[編集]
テレビ[編集]
アインシュタインの眼(NHK-BShi)構成企画参加 2007年9月4日「土壁は生きている」
2008年2月19日「ネイチャーテクノロジーの世界」
KHBグリーンキャンペーン特別番組「宮城発!青い地球を守るために」(東日本放送、2008年8月31日)
ECO LIVE SEBDAI vol.4(東日本放送、2009年3月20日)
ワールドビジネスサテライト(テレビ東京、2009年3月24日)「さまざまなネイチャーテクノロジーのビジネスへの可能性」
スーパーJチャンネルみやぎ(東日本放送、2009年5月5日・6日・6月9日・7月21日・8月21日・2012年2月8日)「未来研究室」
動物びっくり能力 TOP30(テレビ東京、2009年8月4日)解説コメンテーター
世界を変える100人の日本人(テレビ東京、2009年10月16日)「“自然”から教えてもらう 科学者」
新感覚ゲーム クエスタ(NHK総合テレビ、2010年4月8日)
知っとこ!(毎日放送、2010年9月4日)
ニュースウォッチ9(NHK総合テレビ、2010年10月28日)
夢の扉 〜NEXT DOOR〜(TBS、2010年12月12日)「自然の力から得る研究で未来を変えて行きたい」
飛び出せ科学くん(TBS、2011年3月5日)
情報満載ライブショー モーニングバード!(テレビ朝日、2011年8月1日・2012年1月23日)「スタイルアップ!アカデミヨシズミ」
震災を語る(TwellV、2011年8月14日)
時論公論(NHK総合テレビ、2011年9月19日)
突撃!ナマイキTV(東日本放送、2012年2月14日)
クローズアップ現代(NHK総合テレビ、2012年3月14日)「90歳が変える未来のテクノロジー」
テストの花道(NHK教育テレビ、2012年6月25日)「東北大学キャンパスツアーPART2」
サイエンスZERO(NHK教育テレビ、2012年11月11日)「バイオミメティクス 生物が秘める超絶能力をいかせ!」
その他メディア[編集]
インタビュー(GreenTV Japan、2010年4月19日) - 「ネイチャーテクノロジー(石田秀輝教授)」
語る vol.38(dff.jp) - 「石田秀輝」
かしこい生き方のススメ(NTTコムウェア、2007年2月) - 「自然のすごさに学ぶ 新しいものつくりの形を提案したいのです」
キーパーソンインタビュー(環境goo) - 「株式会社INAX 取締役 技術統括部長 石田秀輝氏 インタビュー」
生物多様性COP10(グッドニュース・ジャパン、2008年3月5日) - 「ネイチャーテクノロジーで環境負荷を最小限に」
VISION(WORKSIGHT、2012年2月20日) - 「リーダー層に求められるバックキャストの思考法」
製品・技術を開発する(J-Net21、2012年7月4日) - 「自然から学ぶアイデアの源泉 ネイチャーテック」
脚注[編集]
[ヘルプ]
1.^ EPOC環境コミュニケーションシステム [企業が、その規模、業種、業態に関係なく自らの環境への取組を自己宣言し、自己達成・自己進化するガラス張りのコミュニケーションシステム]
2.^ すごい自然のショールーム
3.^ 持続可能なライフスタイルデザイン手法 [90歳ヒアリングを生かした街づくり:90歳ヒアリングについて]
関連[編集]
東北大学の人物一覧
外部リンク[編集]
東北大学大学院 環境科学研究科 石田研究室
東北大学 研究者データベース:石田 秀輝
石田 秀輝 - 研究者 - ReaD & Researchmap
すごい自然のショールーム
地球村研究室(公式ブログ)
23:11 2014/03/20
篠原 孝(しのはら たかし、1948年7月17日 - )は、日本の政治家。民主党所属の衆議院議員(4期)、民主党副幹事長。
農林水産副大臣(菅内閣・菅第1次改造内閣・菅第2次改造内閣)、民主党国会対策副委員長などを歴任した。
http://www.shinohara21.com/blog/
目次 [非表示]
1 来歴
2 現在の役職 2.1 衆議院
2.2 民主党
3 人物
4 政策
5 所属団体・議員連盟
6 著書 6.1 単著
6.2 博士論文
6.3 編・解説
6.4 共著
6.5 共監修
6.6 共監訳
7 脚注
8 外部リンク
来歴[編集]
長野県中野市生まれ。長野県長野高等学校、京都大学法学部卒業。京大卒業後、農林水産省に入省。経済協力開発機構(OECD)日本政府代表部参事官、農水省農林水産政策研究所所長などを経て、退官。農水官僚時代は日本で初めてフードマイレージの概念を提唱し、日本の食に関する問題に携わった。
2003年、第43回衆議院議員総選挙に民主党公認で長野1区から出馬。長野1区では自由民主党公認の小坂憲次に僅差で敗れたが、重複立候補していた比例北陸信越ブロックで復活し、初当選した。当選後、1年生議員ながら衆議院予算委員会に所属し、BSE問題について首相の小泉純一郎や農林水産大臣の武部勤に対して質疑を行った。
2005年の第44回衆議院議員総選挙では、長野1区で再び小坂に敗れたが、比例北陸信越ブロックで復活し、再選。2006年9月より、民主党次の内閣でネクスト農林水産大臣を務め、農家への戸別所得補償制度の立案に携わる。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、長野1区で小坂を破り、初めて小選挙区で当選した。
2010年、菅内閣で農林水産副大臣に任命され、菅第2次改造内閣まで務める。2011年9月の民主党代表選挙では、現職の農林水産大臣であった鹿野道彦を支持し、代表選出馬に際して鹿野が旗揚げした素交会の結成に参加(鹿野は野田佳彦らに敗れ、1回目の投票で4位に終わった)。野田内閣発足に伴い農林水産副大臣を退任し、民主党副幹事長に就任。
2012年、消費税増税法案を含む社会保障・税一体改革関連法案の衆議院本会議における採決では、投票を棄権した。同年12月の第46回衆議院議員総選挙には民主党公認、国民新党推薦で出馬。与党に猛烈な逆風が吹き荒れる中、長野1区で自民党新人の小松裕、日本維新の会新人の宮沢隆仁を下し、4選を果たした。
現在の役職[編集]
衆議院[編集]
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会理事
予算委員会委員
議院運営委員会委員
民主党[編集]
常任幹事(北陸信越)
副幹事長
国民運動委員会副委員長
長野県第1区総支部長
人物[編集]
元衆議院議員で名古屋市長の河村たかしは、かつて議員会館での部屋が隣同士だった間柄で親しく、河村に誘われ議員年金廃止議員連盟に加盟していた。また、民主党代表選挙に際しては「河村たかしを一度でいいから代表選に出す会」会長を自称し、毎回河村の推薦人に名を連ねたが、結局河村は一度も立候補に必要な20人の推薦人を集められないまま、名古屋市長選出馬のため2009年に衆議院議員を辞職した。
2008年6月12日、前原誠司が農家への戸別所得補償について否定的なコメントを述べたことに対し、「前原誠司副代表の妄言を糾弾し、その『退場』を勧告する」と題したメールを、ネクスト農林水産大臣経験者である筒井信隆、山田正彦、篠原の連名で民主党所属議員に配信した。
2009年5月6日、1932年に中国で起きた平頂山事件について日本政府に公式謝罪を求める議員団に参加した[1]。
政策[編集]
選択的夫婦別姓制度導入に賛成[2]。
恒久平和調査局設置法案に賛成。
集団的自衛権の行使に反対。
所属団体・議員連盟[編集]
立憲フォーラム(呼びかけ人)
著書[編集]
単著[編集]
『アメリカは田舎の留学記 - 霞ケ関いなかっぺ官僚』(柏書房、1983年)
『農的小日本主義の勧め』(柏書房、1985年→新版、1985年→創森社、1995年)
『第一次産業の復活 - 森と水と土の世紀』(ダイヤモンド社、1995年)
『EUの農業交渉力 - WTO交渉への戦略を練る』(農山漁村文化協会、2000年)
『農的循環社会への道』(創森社、2000年)
『花の都パリ「外交赤書」』(講談社+α新書、2007年)ISBN 4062724413
『TPPはいらない! - グローバリゼーションからジャパナイゼーションへ』(日本評論社、2012年)
『原発廃止で世代責任を果たす - 放射能汚染は害毒 原発輸出は恥』(創森社、2012年)
博士論文[編集]
『EUのUR農業交渉とCAP改革における政策決定プロセスの研究』(農学博士、乙種、2001年、京都大学、農山漁村文化協会、2000年9月)ISBN 4540001213
編・解説[編集]
『日本農業100の意見100の主張 - 農業・農政提言集』(柏書房、1987年)
共著[編集]
『飽食のかげの星条旗』(森永和彦との共著、家の光協会、1982年)
共監修[編集]
『食糧超大国の崩壊 - アメリカ農務省特別調査報告』(唯是康彦との共監修、家の光協会、1982年)
共監訳[編集]
『食糧超大国 - 食糧は十分にあるだろうか アメリカ農務省特別白書』(嘉田良平との共監訳、家の光協会、1982年)
2.^ mネット 2004年2月 国会議員への民法改正に関するアンケート
外部リンク[編集]
16:59 2014/03/20
中小建設企業のIT化99のツボ―これだけは知っておきたい! [単行本]平 智之
(著)
内容紹介
『これだけは知っておきたい 中小建設企業のIT化 99のツボ』(略称 ツボ本)は、中小建設企業の経営者、事務・営業の方、現場技術者に向けた、実践的なIT入門書です。電子申請・電子入札・電子納品から、ITを活用した経営革新まで、「これだけは知っておきたい」という「99のツボ(ポイント)」を解説しています。同書には、「IT化によって、建設市場縮小という逆境を好機に転じる」戦略が示されています。
「IT化でコストダウンはできるのでしょうか?」「パソコン1台で電子入札に対応できますか?」「電子入札はすべて一般競争入札でしょうか?」「工事請負契約は電子契約できるのですか?」「SXFってなんですか?」などの疑問に、イラストを豊富に用いて、分かりやすく答えています。
著者の平智之氏(アドミックス代表取締役)は、中小建設企業への経営コンサルタントとして活躍するほか、建設業振興基金の「ITを活用した民間建設工事発注者支援システム研究会」など各種委員会の委員、東日本建設業保証、西日本建設業保証の講師も務めています。本書は、公共事業に携わる皆様、必読の本です。
著者からのコメント
いま、地域建設産業はふたつの激流にのみこまれています。ひとつは市場規模の縮小であり、もうひとつはIT化の進展です。いずれも予想をはるかに超えるスピードで進んでおり、当面その勢いをとどめることはできそうにありません。市場規模の縮小に異論を唱えても、IT化の問題を指摘しても、生き残りをかけた戦いに勝利することはできないでしょう。こういう時こそ逆転の発送が必要です。ふたつの激流を逆境ではなく好機と捉える発想です。戦略的なIT化によって、市場規模の縮小を逆境ではなく好機に転じる戦略が求められています。
以上の問題意識から、本書では中小建設企業の経営革新を生み出すためのIT化戦略をご紹介しています。パソコンの操作方法やソフトウェアをご紹介するのではなく、IT化による経営革新の戦略をご提案しています。本書はマニュアル書ではなく、戦略書です。
単行本: 205ページ
出版社: 建通新聞社 (2005/06)発売日: 2005/06
目次
第1章 IT化のツボ
第2章 CALSのツボ
第3章 電子申請のツボ
第4章 電子署名のツボ
第5章 電子入札のツボ
第6章 電子契約のツボ
第7章 電子納品のツボ
第8章 IT用語のツボ
付 章 公開鍵暗号方式
8:48 2014/03/15
なぜ少数派に政治が動かされるのか? (ディスカヴァー携書) [新書]平 智之 (著) 5つ星のうち 4.6 レビューをすべて見る (5件のカスタマーレビュー)
内容紹介
原発行政をはじめ、年金や教育、生活保護、公共投資、治安、成長戦略等々、
あらゆる場面で少数の利権集団が官僚や政治家をうまく使いこなして政治を動かしている。
また、日本の多数派は「もの言わぬ多数派」であり、少数派が流す誤った情報に左右され、 彼らの意見に消極的に賛成する存在になってしまっているという問題もある。
少数派は富を集中させるため、非効率な社会をそのままにしておきたいのだ。
多数派よ、目覚めよ! そうすれば事態はすぐにも変わる。
この国で何が起こっているのか、それを止めるにはどうすればいいかを国会議員を務めた理系ビジネスマンが論じる。
〈帯コピー〉
原発推進派はたった0.6%!?それでも原発が止まらない不思議国会議員だったから見えた政治のカラクリ。ここからどうする?
内容(「BOOK」データベースより)
原発行政をはじめ、年金や教育、生活保護、公共投資、治安、成長戦略等々、あらゆる場面で少数の利権集団が官僚や政治家をうまく使いこなして政治を動かしている。また、日本の多数派は「もの言わぬ多数派」であり、少数派が流す誤った情報に左右され、彼らの意見に消極的に賛成する存在になってしまっているという問題もある。少数派は富を集中させるため、非効率な社会をそのままにしておきたいのだ。多数派よ、目覚めよ!そうすれば事態はすぐにも変わる。この国で何が起こっているのか、それを止めるにはどうすればいいかを国会議員を務めた理系ビジネスマンが論じる。
新書: 180ページ出版社: ディスカヴァー・トゥエンティワン (2013/7/7)
言語: 日本語発売日: 2013/7/7
目次
はじめに 少数派の情報が、多数派の意見を形成している!
第1章 多数派の声「原発ゼロ」が実現しない理由たった0・6%の少数派が国を動かすシステムとは一握りの人間が、大多数の国民を翻弄している原発をなぜ禁止しなければいけないのか効率的なやり方が歓迎されない理由 戦時統制経済がいまだに続いている マジョリティの意見というものはどのように形成されるのか少数派もこのチキンレースを楽しんでいない
第2章 経済弱者の声が政治に届かない政治家には事務局の声しか届かない現実がある誰もが破綻していると知っている年金制度 必要なのは抜本的改革のための議論なのだが…
最低賃金ではなく透明化が大事 伝統工芸を守るために一部国営化も考えたい
第3章 増税は大きな間違いだと気づくべき金持ちから税金を絞っても、富の再配分は起こらない減税政策の意味を国会議員でさえほとんど知らない参加型民主主義という理想に向かって歩み始めたい中央集権的土建国家からの脱却が急務 「地域の仕事は地域で行いたい」が多数派の意見 相続税ゼロがなぜ地域を富ませるのか都市経済を中心とする地方分権化を提案する!
第4章 日本の成長戦略に必要なグランドデザインを考える大学受験はなぜ年1回しかできないのか?
徒弟制度を前提とした人材の流動化という対案 延命ではなく、再チャレンジのしやすいビジネス環境を作る「千三つプロジェクト」で日本経済を活性化する
第5章 政治家の通信簿はどうつけるべきか議員立法のマジックに踊らされてはいけない
議員の立場、議員の本懐、政治家の汗のかき方 「議員に知恵をつける」くらいの姿勢で接してほしい働かない人間を働かせるのも政治 現代版・頼母子講の復活も妙案かもしれない いかなる原理主義にも与してはいけない国会議員=政治家が行政側に立ってしまう瞬間 多数派は、本当に多数派だろうか?
おわりに 議員歳費ゼロでいいから官僚OBを雇いたい
利権を握る少数派による「多数派工作」を可視化, 2013/7/7
安冨歩 (東京都) - レビューをすべて見る
レビュー対象商品: なぜ少数派に政治が動かされるのか? (ディスカヴァー携書) (新書)
平智之氏は、工学者→喫茶店マスター→ラジオ・パーソナリティー→テレビ・コメディアン→経営者・経営コンサルタント→衆議院議員(1期で落選) という波瀾万丈の多彩な経歴を誇る。本書は、京都大学・UCLAとで学んだ幅広い知識と、多様な経験によって養った健全な常識とで武装した好奇心溢れるこの人物が、衆議院議員として国会周辺をフィールドワークした貴重な報告書である。
本書は、この日本政治の中枢領域が、如何に非常識な形で構成され、運営されているかを明らかにしている。利権をつかんだ少数派が「事務局」を作って自分たちに都合の良い構造を作り出し、その権益の一部を広く薄くばらまくことで「共犯者」を大量に形成し、さらにウソを垂れ流して「多数意見」を作り出す。原発・教育・年金・医療・公共事業・・・何もかもが同じ手口で構造化されてしまっていることが、日本社会を破綻へと導いているのである。
夕食後にあっという間に読める。選挙に行く前に読んだほうが良い。
5つ星のうち 5.0 なぜ民主党政権はこうも簡単に瓦解したか-民主党から離脱した異色政治家の考察, 2013/7/25
レビュー対象商品: なぜ少数派に政治が動かされるのか? (ディスカヴァー携書) (新書)
民主党の政治家として、大多数の民意を政治に反映させようとしながら、少数の利害関係者の影響力の前に結果を残せなかった現実を前に、ロジカルにその敗因を分析している。白眉はP171の「国会議員=政治家が行政側に立ってしまう瞬間」だろう。
今後、民主党が息を吹き返すことはなかろうが、民主党にも筋の通った政治家がいたと知ったのは救いである。
政治家とはかくあるべしということを率直に語っている。何かイベントが起こったときにその場に駆けつけるのは、関係者には喜ばれる<選挙に有利>だろうが、それが最も有効とは限らない。政治家であれば政治家としてもっとできることがあるという主張だろう。
日本の社会構造(官僚制/重層構造/年金制度/所得再分配など)の整理も見事。
5つ星のうち 4.0 面白い視点の本, 2013/8/21
レビュー対象商品: なぜ少数派に政治が動かされるのか? (ディスカヴァー携書) (新書)
著者の計算によれば、原発推進派は国民の僅か0.6%に過ぎないという。それなのに原発推進を明言した自民党が2013年の参院選で圧勝し、安倍総理の海外への原発セールス行脚も含めて原発回帰が明確である。
この原発を例に、少数意見が国を動かすことになるメカニズムを解き明かそうという狙いは面白い。
著者の言うメカニズムとは、
1.一部の銀行や巨大企業、大企業の労働組合などの巨大組織の声だけが政治家に届くシステムがあること
2.少数派の特権階級(政治家、企業、マスコミ、学者など)の流す意図的に誤った情報に多数派が左右されやすいこと
3.誤った情報に操作された多数派の多くは、本来の自分の意見を封印し、あえて少数派の意見に消極的に賛成する人々(ネガティブ・サイレント・マジョリティ)であること
などである。
1.に関しては、例えば反原発で言うとNPOや任意団体では、素晴らしい理念はあるのだが、具体的な政策提言や財源案がない。しかも団体の数が多く、それぞれの主張が微妙に異なり、一つの力として結集できないという問題もある。
それに対して各省庁の官僚は、関連する業界の事務局からの要望を受け、利権のために一生懸命に働いて見事な事業計画を作り上げる。議員はどうしても実現性の高いそちらの計画を聞いてしまう、とのことだ。
本の後半はタイトルから若干離れ、いくつかの政治分野における著者の考えを展開している。税金の取り方と使い方、日本の成長のためのグランドデザイン政治家のやるべきことなど、中々大胆で面白い政策を提言している。
少数派が動かす政治においては非効率であることが好まれるという。非効率であることによって生じる不都合を解消するために、新たな仕事が発生し、官僚の利権が生まれるからだ。
このような非効率な政治が続く限り、国民の不幸は続く。抜本的な改革の必要性を感じさせられた。
5つ星のうち 5.0 政治家としての真摯な実践の書, 2013/8/9
レビュー対象商品: なぜ少数派に政治が動かされるのか? (ディスカヴァー携書) (新書)
利権集団が事務局を作り、豊富な資金と人材をつぎ込んで政治家を洗脳し、天下り先を増殖させる構造を見事に描き出している。いろいろ卓見に啓発された。-仕方がないから「あえて原発に触れるのはよそう」というネガティブ・サイレント・マジョリティーが形成される。-大きな利権に守られている原発の核廃棄物施設などで働いている人は、薄ら笑いしながら極度の緊張と不愉快の中に身をおいている。
-建築業界の多層下請け構造と一人親方の増加がリンクしている。
-小沢幹事長時代に、陳情を幹事長室に一元化する制度を行ったのは良いことだった。
-相続税増税は街を壊す。
-国家予算を減らしたほうが財政赤字が減る。→地方分権
-大学入学時期も卒業時期も年2回とか4回にする。企業の採用時期も増やす。そして人材流動化を促す。
-企業の助成金は延命にばかり使わず、無駄な廃業にも使え。
-議員立法はあまり機能しない。
最後に庶民から聞かされた本当の願いを紹介し、政治家の役目は何かという自問をしておられる。
こういう人こそ再選されるべきなのに、と思う。
イッパツマン (あちらこちら) - レビューをすべて見る
(トップ500レビュアー)
レビュー対象商品: なぜ少数派に政治が動かされるのか? (ディスカヴァー携書) (新書)
著者は元与党新人議員。実際の議員時代の経験を通して、利権集団化した中央官僚組織と国会議員が少数派利権の「事務局」となっていることを、原発、財政、所得分配、福祉、教育(大学や保育園を含む)等、様々な実例で解説した一冊。本書で語られる具体的政策ビジョンには(政治家の著作にありがちな)耳障りの良いラディカルなことは書かれていないが、利権ネットワークが未だ強固な現状では、本書に書かれたような地味な政策でも実現には多大なエネルギーが必要となるであろうことが、十分伝わってくる。
少し気になったのは、著者の描く地方再生構想というのが、彼の地元(京都)のような伝統的商工都市を想定したもので、応用できる地域が実はそれ程多くないように思えること。また、著者(及び彼が現在所属する政党)の掲げる脱中央官僚主義の結果として、公共サービスの担い手として少数精鋭の市町村職員、頼母子講、NPO等が構想されているが、一番肝心なこれらの担い手の選別・育成、ネットワーキングの話というのは殆どない。
「脱官僚」「財政赤字解消」というのは色んな政治家が語っている言葉だが、じゃあ、官僚機構と国家予算無しでどうやっていくのかという話の各論こそ、本書に期待したものだったので、星は一つ削らせてもらった。ただ、戦後に出来上がって固定化した官民利権のネットワークがこの国をいかにダメにしているかという現状整理の本としては、他のレビュアーの皆さん同様、一定の評価をしている。
8:50 2014/03/15
第6部 行政改革の病理学・・・第1章・行政改革失敗の原因・・228・・
うわべだけの鬼退治ゲーム・・228頁・
行政改革を妨げる主犯はクニ・ムラ、つまり各省庁と官僚およびそれを取り巻く行政依存産業の抵抗であるが、そればかりではない。政治家達は、国民のウケを狙いつつも、支持基盤である産業や地域の栄養源である既得権益を枯らさないようにと腐心する。マスコミは、そのセンセーショナリズムから、本質的な議論よりも「見出し」になるトピックスを追いたがる。
そういう思惑が交錯する中で、行革は国民のためという本来の目的をどこかへ置き忘れ、うわべだけの鬼退治ケームと化してしまう。もちろん、人畜に害ある鬼の追放ならば結構の話であるが、抵抗の小さな組織を生け贄にしたり、制度のささやかな手直しでお茶を濁すなど、見せかけの改革で点数を稼ぎ、その陰で本当の鬼たちは巧みに姿を変え、しぶとく生き残ってしまうことが多い。
229頁、
筆者は霞ヶ関に三十二年余り勤務したが、その半分以上の期間は、直接、間接に行政改革や行政運営の改善に携わって来た。したがって、その病理現象をあげつらうことは、それらを克服できなかった自らの非力さ、無能力ぶりを告白することに外ならず、内心忸怩たる思いを禁じ得ないが、あえてえその恥を晒すことによって、行革の進め方に一石を投じることができれば幸いという考え、本稿を起こすこととした。
まず、議論の過程に焦点を当てよう。
「改革を妨げるキーワード」
総論賛成・各論反対
よく知られているように、論議の過程における特徴的な現象は、「総論賛成・各論反対」である。行政の評判が悪く大きな不合理とムダがあることや財政が破綻状態にあることは、全ての公務員に自覚されている。それに一市民の立場に戻れば、お役所仕事に悩まされることも多いから、改革は当然必要と考えられている。しかし、自分の体臭、異臭には気がつかないものだし、顔を利かせて特別に便宜を図ってもらうという裏技に長けている彼等は、自らの国・村に関わる問題で苦労をした経験がないから、批判の目を内側に向けることはなく、改革といえば、他の役所のことと考えている。
230頁、
かつて、ある新聞が、霞ヶ関の課長クラスを対象に、行革の実現可能性についてのアンケート調査を行ったことがあった。一般の官僚が強気つまり実現可能と考えていたのに対し、行革を担当していた行政管理庁(当時)の幹部に弱気な者が多いことが批判されていたが、実は各省庁の幹部達が断行すべきと考えていた改革とは、他省庁のことだったのである。同様に、第二臨調の事務局は、各省庁の職員の混成部隊であったが、農林水産省からの出向職員が運輸省(当時)の許認可件数の多さをあげつらえば、運輸省の職員は農林水産省の補助金の多さを冷やかすという類の一幕もあった。
大蔵省(当時)の振る舞いも矛盾に満ちていた。歳出の削減を役割としている彼らは行革サイドとは友軍関係にある。しかし、改革案が具体化し、彼らの権益にも影響が及びそうになると態度が豹変した。緊密な協力関係にひびが入るだけではない。たとえば、筆者が会計課長を務めていた際にも、予算を握っている主計局筋から呼び出され、あなたのところの○○氏はやり過ぎではないかと、脅しまがいの忠告を受けたこともあった。
このようなエゴイズムは、審議会に参加している専門委員や参与も汚染していて、ご自分の関係する組織に関わると、とたんに別の顔を見せる人もいた。
231頁、
陰に回って、この問題を取り上げるなら他の分野の改革に協力できないと圧力をかけたのである。
業界や地域団体の対応も良く似ていた。決着や要望書にはもっともらしい改革意見が書かれていても、ここの改革案が表に出ると、訪ねたり、電話してくるのは、反対や特別扱いを求める方ばかり、どこで調べてきたのか、友人や知人まで反対のための陳情に動員して来る。改革を公約にしているはずの国会議員も同様で、中堅や陣笠クラスは、直接泣き落としや脅しに来るし、大物ともなれば、代わりに秘書達がやってきて、こういうことになるとうちの先生は非常に困った立場になると謎をかける。行革に携わると、友人を失い、人間不信になるという話はあながち誇張ではなかった。
○低い相場感・・・
行革といえば、ムダ、ムリ、ムラを減らすことと思われている。もちろん、それらは初歩的な課題ではあるが、それだけではなく、膨れ上がった行政の守備範囲を縮小し、皆で痛みに耐えなければ実効ある改革は実現できない。ところが、霞ヶ関にはそう言う意識、覚悟はほとんどなく、誰の目にも分かるほど優先度や存在感が低下してものを切り落とせば足りる、難し問題なら一歩ずつ改善していけばいいという相場感があり、これも改革を妨げてきた。
あの土光さんですら、当初はそんな感覚だったらしい。第二臨調会長をお引き受けいただいた後のある日、「会計検査結果を見ると、たった八%の抽出調査で、5,000億円のムダが明らかになっている。
232頁、
全部洗い直せば、六兆円くらいの節減はすぐにできる」とテレビで語られていた。検査結果を伝える新聞の見出しだけを見れば、そう受け取られるのはやむ得ないが、五千億円の大部分は手続きに関わる不適正経理で、節約できる金額ではなかったし、抽出率も調査対象事業所ベースの話で、金額ベースなら約30%になる。上司に相談したら、君が言って説明して来いというので、初めて二人きりでお目にかかり、新聞記事のカラクリを説明した。
話を聞かれた会長は、この中で節約可能な金額はどの位かと問われたので、せいぜい二、3百億円程度ではないかと申し上げたら、憮然とされたご様子だったが、後刻、このことを会計検査院長に直接確認され、改めてフンドシを締め直されたようであった。
土光さんは、お亡くなりになるまで、お目にかかるつど、君には世話になっとと言われたが、答申の中身で、褒められるほどの働きをした覚えはなく、この一件のことだったと思っている。
こんな思い違い、つまり行革とは小さな悪鬼を退治すること、麻雀でいうハジパイを切るようなものだという相場観は、改革に当たる側も汚染していた。たとえば、第二臨調で特殊法人を担当していた筆者は、全法人をマナイタの上に乗せ、その存在理由から問い直す議論を展開したが、改革側の最高責任者であった上司からは、そんな真似をして、本当に火がついたらどうするかと叱られた。当方は火がつくことを期待していたのに、である。
233頁、
等身を終えられた後の打ち上げの席上、筆者は各省庁と政治の抵抗や内部の裏切りによって、多くの課題が掌から漏れてしまったことを悔いていたのに、その上司からは、やりすぎだと皮肉を言われたのも悲しい思い出である。
○根強い横並び意識・・・
行革は政策課題の見直しにまで踏み込まなければ達成駅ないことまでの理解は得られても、具体的な改革案につなげることは容易ではない。その原因は、各省庁が推進している施策が既に時代遅れとなり社会のニーズからかけ離れていることや、コストに比べて効果が小さいこと等を、縦割りの政業官の複合サークルの中で特定の価値観で凝り固まっている方々にご理解いただくことがそもそも困難なことであったが、それに加えて、特殊法人、補助金、許認可などの政策手段を廃止しようとすれば、それらの創設に尽力してきた、いわばドンとでも言うべき有力政治家の顔を潰すことになり、折衝の相手側の立場を著しく損ない、クニ・ムラの中での居心地を悪くするからである。
従って、この種の抵抗を最小限に抑えるためには、横並びの確保が大事な課題になった。他の省庁もやられているからとか、皆お付き合いしているのだから、という弁解が組織内外の抵抗を和らげ、折衝の矢面に立たされた担当者に対する風当たりを減らすからである。これまで、定員の計画削減を初め、一省庁一局削減、一省庁一法人廃止などが実現し得たのはこのためであるが、こういう手法は、含み資産の多い古い省庁に有利に働くという歪みを生むほか、強い抵抗をする省庁が一つでもあれば、そのために全体の改革が頓挫する等の弊害も生んでいる。
234頁、
○理由なき抵抗と情報隠し・・・
改革案をめぐって、激しい論戦が行われるのは当然である。これは、どんなに苦労してもさわやかな疲れを伴う作業であり、お互いの立脚や認識の違いを明らかにしていことによって、思いがけない解決策が見い出せつといった楽しみもある。
ぎゃくに、最も疲れるのは、単に「改革はこんなんである」「勘弁してください」と繰り返すだけの相手との折衝である。問題提起にはほとんど耳を傾けず原理原則論や現行法性の枠組みに固執する連中もこれに似ていた。
こういう手合いに共通しているのは、背後に強力な政治家や圧力団体が控えているため、その意向に反した意思決定ができないことである。もともと役所自体が政官業の複合サークルの法務部程度の機能しか持たず、当事者能力に欠けているから、押し問答するしか芸がなかったのであろう。
議論に負けたくなければ、情報隠しが有力な戦法になる。隠すというよりも、そもそも都合の悪い情報は把握したり、分析しようしないのが彼らの流儀である。生業の庇護と圧力下に安住し、見直しや改革を行うという志がなければ、外部からの批判のタネになる情報など全く無用なのであろう。彼らは時として、ヒアリングの拒否という行動に出たこともあったが、こういう非常識な対応は、行革側が以下に舐められているかということと、抵抗勢力側にいかに自信がないかを物語るのである。
235頁、
このように、籠城作戦をとり原理原則のお題目しか唱えない相手に対しては打つ手が乏しく、状況証拠を積み上げて問題点を指摘し、反撃を待つしかないが、この種の議論に対して、世論は意外に注目してくれない。先年の規制改革推進会議のワーキンググループは公開討論の形で行われ、毎回、大勢の記者たちに取り囲まれながら議論していたが、その内容が記事になることはあまりなかった。彼らの沈黙戦術は、マスコミや世論の無関心にも支えられているのである。
○大石と小石・・・
制度や組織は大きくなるほど潰し難い。囲碁に大石は死なずという格言があるように、大きくなれば防御のために動員できる人材、人脈、資金なども豊かで、逆襲して改革そのものを潰したり、どこか目をもぅって生き延びる可能性が高いからである。
改革側にも先のような相場観があるから、大石を眼前にすると、はじめから無力感やためらいを持つようである。第二臨調における特殊法人改革に際しては、当時の日本開発銀行、日本住宅公団等は、どのような見地から見ても、官の事業として存続する必然性は認められなかったが、議論を開始してみると、友軍側に本気に取り組もうとしない者が多過ぎた。ハジパイから切るという霞ヶ関の常識からすれば、各省庁内において、最も大事にされている法人に手を付けようという議論は暴論に映ったのであろう。
236頁、平成26年3月14日・
もっとも、相手が小さければ改革が行いやすいというわけでもなく、防御側の抵抗は、勝るとも劣らないのが常であった。
大きな組織、制度の場合、世論に叩かれ慣れているし、関係者が多いため防衛責任も分散している。例えば廃止、縮小に追い込まれたところで特定の誰かの責任になるわけではない。ところが、小さな組織、制度の場合、対応は課長クラスに任されている。
背後にいるドンも特定している。戦に負けドンの顔を潰せば、その課長は無能のレッテルを貼られ、回復不可能な損害を破る恐れがあるから、死に物狂いの抵抗が行われるのである。ところで、各省庁の大臣官房は、クニやムらの権益の総元締として、最大限の防御に務める一方、内閣の一員として行革を進めざるを得ない大臣を補佐する立場からは、ある程度の成果を上げざるを得ないというジレンマを抱えている。そこで、改革の矛先をハジパイである小さな組織、制度に誘導しようと試みることもあるが、うっかりその誘いに乗って大汗をかいたことが少なくなかった。
○推進側の足並みの乱れ・・・
推進側の足並みの乱れも、一種の病理現象である、抵抗側の切り崩しが功を奏した例もあろうが、より根本的な原因が横たわっている。
抵抗勢力の陣営は、有無相通ずる元々の仲間であり、守ろうとしているのも権益、実利であるから分かりやすく、その結束力は極めて強い。
237頁、
これに対する推薦し陣営は、突然召集された混成部隊で、お互いの気心もしれていないし、思惑や戦術も違う。それぞれが携えてきた武器も、理論や大義名分など抽象的なものに過ぎないから、議論のタネにこと欠かず、遠心力が働きやすい。
その上、言論による空中戦の際は優勢に見えても、具体的な成果を得るための地上戦になるにつれ、戦況は次第に劣勢になるから、改革の目標や手順、重点、突破口をめぐって、内輪モメや張り合い、先陣争いが起こりやすい。かつての全学連三派系は本来の敵と戦う前に内ゲバで消耗し、自滅して行ったが、その故事を笑えないのである。
筆者も幾度か行革のための会議に参加・関与したが、改革の対象である抵抗側からの反論よりも、本来は味方であるはずの改革側から議論を妨げられた経験が少なからずあった。道路公団改革に際しても、推進委員会は分裂してしまったが、無駄な道路は作らない、債務や通行料等の国民の負担は最小限とするという点では、スタンスの違いの差はなかったはずである。
237・平成26年3月15日・
改革を妨げるキーワード・・229頁、
低い相場観・・231頁、
根強い横並び意識・・233頁、
理由なき抵抗と情報隠し・・234頁、
大石と小石・・235頁、
推進側の足並みの乱れ・・236頁、
第2章・矮小化する改革案・・238・・
行革は内戦・答申案は停戦協定・・
官庁文学の枠としての答申・・240頁、先送り、尻抜け、玉虫色の決着・・・
数合わせ・・241頁、
看板の掛け替えと焼け太り・・242頁、
大河のような抵抗勢力・・243頁、
行政のプロの欠如・・244頁、
おわりに・私の行政改革論・・247・・
1・行政の論理の再構築・・・神話からの脱却・・249ページ、1・行政をめぐる理念の見直し・・
2・完全主義の払拭・・250頁、
3・国家目標を表す指標の開発・・252頁、
4・法令の整理・・254頁、
2・クニ・ムラ体制の解体・・256頁、
1・事務次官制度の廃止・・259頁、
2・官民交流の推進・・261頁、
3・多分野の専門家の活用・・263頁、
意思決定システムの改革・・265頁、
4・地方分権の推進・・特効薬は地方分権・・268頁、
2・地方は能力不足か・・271頁、
現場における総合調整・・273頁、
市町村合併と道州制への疑問・・275頁、
あとがき・277・・
16:19 2014/03/04


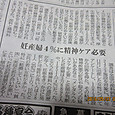

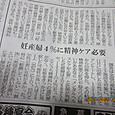



コメント