自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか ・・石田秀輝(著)
引用
自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか (DOJIN選書22) [単行本(ソフトカバー)]石田秀輝(著)
内容紹介
天然のエアコンともいえる土、洗浄不要のカタツムリの殻、どんな表面にもくっつくヤモリの足、ハンマーで叩いても割れないアワビの殻……自然の中には近代テクノロジーでも容易に真似することのできない「知恵」がある。そんな自然を手本にし、江戸時代の粋の構造までも取り込み、省資源・低環境負荷の技術としてデザインし直すのがネイチャー・テクノロジーだ。これは単なる自然模倣ではない。完璧な循環をもつ自然から学ぶ、新しいテクノロジーのかたちである。資源の枯渇が危ぶまれ、地球環境問題が叫ばれるいま、これからのものづくりに何が必要かを考える。
内容(「BOOK」データベースより)
いつも快適なシロアリの巣に学ぶ「無電源エアコン」、汚れ知らずのカタツムリの殻に学ぶ「洗浄不要のキッチン」、天井を走るヤモリの足に学ぶ「あたらしい接着の考え方」―自然のもつ完璧な循環から見えてくるあたらしいテクノロジーのかたち。地球環境をこれまでとは違った角度から捉える。
単行本(ソフトカバー): 232ページ出版社: 化学同人 (2009/1/25)
言語: 日本語発売日: 2009/1/25
目次
あたらしいテクノロジーのかたち――まえがきにかえて
第1章 あたらしく生まれたネイチャー・テクノロジー
1 土に暮らす――無電源エアコン
2 カタツムリに教えてもらう――汚れない表面3 ネイチャー・テクノロジーの予備軍たち
第2章 自然観をもったテクノロジーが必要なのだ
1 あたらしいものづくり文化の創造
2 自ら淘汰を起こし生命文明をつくる
3 テクノロジーへの2つの扉
第3章 地下資源文明から生命文明へ――今こそ第三次産業革命のとき
1 だれのための地球環境問題か
2 地下資源文明から生命文明へ
第4章 人間活動の肥大化が生み出す地球環境問題
1 今の地球の姿
2 地球温暖化は文明崩壊のインジケーター
第5章 近代テクノロジーを支える資源・エネルギーは有限だ
1 化石燃料への依存は続く
2 金属資源だって有限だ
3 ターニングポイントは2030年
第6章 一歩先ゆく粋なテクノロジー
1 テクノロジーはなんのためにあるのか
2 自然を奴隷にした近代テクノロジー
3 自然との和合
4 ネイチャー・テクノロジー――日本発、精神欲をあおる粋なテクノロジー
第7章 ネイチャー・テクノロジーを生み出すシステムが必要だ
1 ネイチャー・テクノロジーをつくる4つの要素 2 ネイチャー・テクノロジー創出システム
第8章 2030年に向けて鳥の目をもった人材が必要だ
1 求められる鳥瞰的視野
2 求められる日本から見た世界観
第9章 ネイチャー・テクノロジーの卵たち
1 軽く、強く、しなやかな自然
2 くっつく、離れるを自在に操る自然
3 光で色を織り成す自然
4 水を導く自然
5 自然が作る糸の不思議
6 病気を治し、人を癒す自然
7 極限の中を生きる自然
目から鱗の一冊でした!! 地球環境問題というと悲観的な評論ばかりで、対策というとレジ袋やお風呂のお湯・・・我慢ばかりで夢のない話ばかり・・・・一体どうしたらよいのかと思っていました。「粋」という言葉に惹かれて手にとってみましたが、本当に眼から鱗の落ちる想いでした。地球環境問題とは人間活動の肥大化であって、その結果、地球温暖化や資源の劣化が起こっていること、そして、この問題を解決するためには、心豊かに暮らしながら新しいライフスタイルをつくらなければならないこと、そのためには、従来型のテクノロジーではなく自然観を持った、あたらしい粋なテクノロジーが必要なこと。断片的な、地球環境に関する情報が一挙に繋がりました。おまけに、避けられない地球環境の劣化に向かっても決して夢を捨てる必要がないことに、心から元気付けられました。素晴らしい一冊に巡り会えたことを感謝しています!!
5つ星のうち 1.0 具体的に我々は何をしたらいいのか?
著者は産業革命以降のテクノロジーによって「エネルギーや資源の消費は幾何級数的な拡大を起こし、地球環境の劣化による文明崩壊の危機を迎えようとしている。」と問題提起し、これを回避するためには「産業革命以来続いた地下資源文明と決別し、太陽と自然の恵みを生かす生命文明創出に求められるネイチャーテクノロジーによらなければならないという。著者は、この本のなかで自らの説を裏付けるデータを示しながら、ネイチャーテクノロジーとは何かを展開します。しかし引用する資料やデータは著者の説を裏付けるかのように取り扱われ、また、ネイチャーテクノロジーを構築するためには何をするのかが具体的にはこの本の中では出てきません。...
なった」と投票しています。
5つ星のうち 5.0 目から鱗の一冊でした!!, 2009/3/9
レビュー対象商品: 自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか (DOJIN選書22) (単行本(ソフトカバー))
地球環境問題というと悲観的な評論ばかりで、対策というとレジ袋やお風呂のお湯・・・我慢ばかりで夢のない話ばかり・・・・一体どうしたらよいのかと思っていました。「粋」という言葉に惹かれて手にとってみましたが、本当に眼から鱗の落ちる想いでした。地球環境問題とは人間活動の肥大化であって、その結果、地球温暖化や資源の劣化が起こっていること、そして、この問題を解決するためには、心豊かに暮らしながら新しいライフスタイルをつくらなければならないこと、そのためには、従来型のテクノロジーではなく自然観を持った、あたらしい粋なテクノロジーが必要なこと。断片的な、地球環境に関する情報が一挙に繋がりました。おまけに、避けられない地球環境の劣化に向かっても決して夢を捨てる必要がないことに、心から元気付けられました。素晴らしい一冊に巡り会えたことを感謝しています!!
5つ星のうち 5.0 ものづくりからことづくりへ、テクノロジーのパラダイム
レビュー対象商品: 自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか (DOJIN選書22) (単行本(ソフトカバー))
これまでのテクノロジーは種々の使用目的を持つ「モノ」を大量に造ってきた。その結果造ることでエネルギーを消費すると共に、個人個人が大量のモノに囲まれ、それを使うために更にエネルギーを消費し、ついには、現在の温暖化や資源の欠乏を招いてしまった。
そのようなモノ造りから造るのにも使うのにもエネルギーを消費しない、モノではなく「(種々のサービスを提供するという)コト」を造るという生産方式が今後の向かう方向であり、これまでのモノ造りを支えてきた考え方を変える、つまりテクノロジーのパラダイムシフトが今後の世界に必要であることを述べたのがこの本だと思う。
つまり、9章で述べられているテクノロジーはこれまでの思考方法とはまるで次元の違った考え方で実行されるべきだということを知ってもらうために1章から8章があるように感じた。このような読み方をした読者にとっては、本当に興味深い本であった。
5つ星のうち 5.0 エコな若者へのメッセージ, 2009/3/22
レビュー対象商品: 自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか (DOJIN選書22) (単行本(ソフトカバー))
ヤモリはなぜ天井を走り回れるのだろうか。魚、アワビ、カタツムリ、シロアリ、ウジ、クモ、カイコ・・・・・・小さな生き物の不思議な技が出るわ出るわ。これらを呼び水として、人々が生きることを楽しんで暮らすためのテクノロジーについて読者に考えさせている。
石油が枯渇に向かい、現有埋蔵量を使い切る金属もみられるという2030年がターニングポイントと指摘する等、未来を生きる子たちのために奮闘する著者の危機意識が伝わってくる。
5つ星のうち 4.0 自分の立ち位置を確認するための本, 2009/3/6
レビュー対象商品: 自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか (DOJIN選書22) (単行本(ソフトカバー))
安井至さんのサイトの紹介を見て買った。環境問題に対してどのようなスタンスの人たちがこの本を手にするか、よくわからないが、私には2~8章は冗長過ぎた。私が読みたかったのは9章である。恐らくおそらくほとんどの(理系の)人は、9章の内容を目当てに購入するのではないか?
行き過ぎた西欧型のテクノロジー論や資源・エネルギー論を論ずるのはいいが、この本を手にする人には耳タコで、そこはさらりと流してほしかった。
ただし、身の丈の生活を希求するヒトには、テクノロジーと自分との距離を確認する意味で、悪い本ではないと思う。最後にひとつ。この挿絵はこの本には合わない。
5つ星のうち 4.0 きづきと工夫, 2009/5/7
レビュー対象商品: 自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか (DOJIN選書22) (単行本(ソフトカバー))
9章の様々な驚きの事例インデックスにとどまらず日本の独自性を軸に新たなテクノロジーへと舵を切るべきとの著者の考え方に共感をおぼえた。日本という方法は昨今多くの本が出ているが著者がよってたつ「粋」に代表される文化だけでなく、いろいろな切り口/(文中目についた「入口のドア」という表現をされているが)により新たな展開やきずきが読み手側にもあるやに感ずる。 雑誌のような形やTVでビジュアルでみたいページがいくつもあったので今後さらに小学生の子供たちが手に取れるような本や動画にも期待する。
5つ星のうち 5.0 持続可能な社会構築への新たな手引書, 2009/3/30
レビュー対象商品: 自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか (DOJIN選書22) (単行本(ソフトカバー))
最新の知見をベースに環境問題の深刻さを非常にわかりやすく伝えている。
このままではいけない、自分も何か行動をしなければという強い衝動に駆られた。
環境問題の深刻さを伝える書籍は数多く存在するが、この一冊を読みとおすことで、環境問題の全体像を体系的につかむことができる。専門家のみでなく、これから環境問題を学ぶ社会人や学生にもぜひお勧めしたい一冊である。
ネイチャーテクノロジーの事例についても数多く書かれ、初心者にもわかりやすく解説している。自然のずごさをあらためて実感した。自然から学び、生き生きと生きることができる社会。そんな社会のイメージを浮き彫りにしている。
5つ星のうち 5.0 味が出る本, 2009/3/15
レビュー対象商品: 自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか (DOJIN選書22) (単行本(ソフトカバー))
『自然に学ぶ粋なテクノロジー』は、読めば読むほど味がでてくる本だと思う。人間社会がどのように地球環境問題をとらえて、何を考えて、舵を取らなければならないかが書かれてある。これまで人類は地球上で生存することを目的として、人間活動を拡大していったが、その拡大を制御することなく、限界を超えて肥大化してしまった。人類は方向転換して、ぎりぎりのソフトランディングをすることが可能なのか。この解を探すために考えなければならないのは、地球環境問題の構造、自然観、文明、文化、テクノロジー、経済社会システム、鳥瞰的視座であることを指摘した本である。昆虫だけ考えればよいのではない。文化を守ることだけ考えればよいわけではない。経済システムだけ考えればよいわけではない。自分のことだけを考えればよいのではない。さらに、この本のメッセージは、「環境負荷を下げるために自然が保有する低環境負荷のテクノロジーを生み出すといいですね」、ということではなく、「人類生存の解があるとすれば、自然が保有するテクノロジーに文化的要素(例えば、「粋」)をのせるという考え方が鍵だ」、ということではないか。将来のものづくりの姿が浮かび上がる。この本は企業や行政機関の新入社員教育や社内勉強会などに有効であろう。
5つ星のうち 1.0 具体的に我々は何をしたらいいのか?, 2011/8/20
レビュー対象商品: 自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか (DOJIN選書22) (単行本(ソフトカバー))
著者は産業革命以降のテクノロジーによって「エネルギーや資源の消費は幾何級数的な拡大を起こし、地球環境の劣化による文明崩壊の危機を迎えようとしている。」と問題提起し、これを回避するためには「産業革命以来続いた地下資源文明と決別し、太陽と自然の恵みを生かす生命文明創出に求められるネイチャーテクノロジーによらなければならないという。著者は、この本のなかで自らの説を裏付けるデータを示しながら、ネイチャーテクノロジーとは何かを展開します。しかし引用する資料やデータは著者の説を裏付けるかのように取り扱われ、また、ネイチャーテクノロジーを構築するためには何をするのかが具体的にはこの本の中では出てきません。
今のテクノロジーに決別しようとしている人たちがいる例として、P52では「一万円近くもする高級な箒の売行きも好調だという。掃除機から箒への淘汰も始まっているのかもしれない。」とありますが、これは、その人の趣味の問題と私は理解します。また、P58の「現在の電子部品を使っても再現に苦労するほど高度で精密なテクノロジーの集積である江戸時代のからくりの数々、・・・」とありますが、今のIT技術を駆使すればそれほど難しいことではありません。また、P57の「たたらによって作られた鉄の高品質」の記述は読者に対して誤解を与えます。現在の製鉄技術でも同じ品質のものを作ることはできます。要はコストの問題です。
「自然」「コミュニケーション」「愛着」「簡明」がネイチャーテクノロジーの4つの要素。このネイチャーテクノロジーを構成する四つの要素を計るものさしを作ることができれば現在のテクノロジーに何を加え、何を削ればよいのかも見えてくるはずである、と著者は持論を展開するが、具体的に何をするのかは全く記述がありません。著者が進める研究ではまだ何も見えてこないのでしょうか。
興味を引いたのは、カタツムリの殻や蜘蛛の糸などなど、多くの自然や生物が持つ素晴らしいテクノロジーの解説です。この自然の技術を人が作るためには多くのエネルギーと資源を必要とし、また実現したとしても環境を破壊しないといえるのでしょうか。
5つ星のうち 2.0 やっぱり理系楽天主義, 2009/4/19
レビュー対象商品: 自然に学ぶ粋なテクノロジー なぜカタツムリの殻は汚れないのか (DOJIN選書22) (単行本(ソフトカバー))
う~ん・・・、科学への過信を戒めてはいるものの、それでもやはり本書は数多くの類書同様、典型的な理系楽天主義に支えられているように思えてなりません。「地球環境問題の解は、人間活動の幾何級数的な拡大を物質的・精神的にいかに収束させるかにある」と正しい指摘をしておきながら、本書で述べられる精神面での解決策(古き良き日本精神への回帰)はあまりにも陳腐です。人間の心を科学でコントロールすることこそ、今日最も緊急な課題なのではないでしょうか。
23:22 2014/03/20
地球が教える奇跡の技術 [単行本(ソフトカバー)]石田秀輝+新しい暮らしとテクノロジーを考える委員会 (著)内容紹介
「ネイチャー・テクノロジー」とは「自然の本質を見きわめ、自然のすごさを賢く活かす技術(テクノロジー)」のこと。
46億年の地球史の中で、淘汰を繰り返しながら「完璧な循環を最も小さなエネルギーで駆動している自然」をサイエンスの目で見直し、まったく新しいものつくりや暮らし方を提案する。
すでに実用化されている「ネイチャー・テクノロジー」の好例が「カタツムリの殻」から生まれた「汚れないタイル(表面素材)」。ビルの外壁やキッチンのぬめりのような汚れを掃除するには大量の水が必要だが、カタツムリは雨に濡れるだけですべての汚れを取り去ってしまう。だからカタツムリの殻をタイルなどの表面素材にできれば、少量の水で汚れを落とすことができるかもしれない。
この発想から、「ネイチャー・テクノロジー」はカタツムリの殻の構造を研究し、「汚れがつきにくく、水だけで取れやすい」セラミックスのタイルやキッチンシンクを生んだ。
著者は、こうした「ネイチャー・テクノロジー」を世界に先駆けて実践できるのは日本人だと主張する。日本人が自然と寄り添いながら生活し、文化を築いてきたからだ。「ネイチャー・テクノロジー」の世界をQ&A形式で平易に解説することで、地球環問題への理解がより深まる本。
カバー画は松本零士
著者について東北大学大学院環境科学研究科教授。1953年生まれ。INAX技術統括部空間デザイン研究所所長などを経て現職。専門は地質・鉱物学をベースとした材料科学。1997年から「人と地球を考えた新しいものつくり」を提唱。多くの実戦経験をもとに、『自然のすごさを賢く活かす』ものつくりのパラダイムシフト実現に国内外で積極的に活動している。2005年9月にはネイチャーテック研究会を発足、あたらしいものつくりの研究・啓発活動も開始した。(共同執筆者:新しい暮らしとテクノロジーを考える委員会 古川柳蔵・エクベリ聡子・菊地辰徳・大西梨沙)
単行本(ソフトカバー): 256ページ出版社: 祥伝社 (2010/3/16)
言語: 日本語発売日: 2010/3/16
目次
1 ネイチャー・テクノロジーの基本を知ろう
カタツムリの殻、シロアリの巣、トンボの羽……「自然に学ぶ」とは、どういうこと?
2 今、必要な知恵はすべて自然の中にあった
「ネイチャー・テクノロジーの卵」を見つけに行こう
3「豊かに生きること」は「ライフスタイルを変えること」エコのために「暮らし方のかたち」を変えるには、どうしたらようのだろう
4 経済の発展と地球環境は、どちらが大切?「金融恐慌」「デフレ」「鈍る成長」……私たちにとって本当の豊かさとは何なのか考えてみよう
5 環境問題の「ウソ」と「真実」環境にまつわる情報洪水の中で、私たちはどのような目を持つべきなのだろう
6 テクノロジーの進歩と地球への負荷を考える「便利さ」と引き換えに、私たちは何を失ったのか。技術はこのまま進歩してもよいのだろうか
7 自然の恵みを「ものづくり」へ地球というシステムが、文明を生き返らせる
8 「粋(いき)なテクノロジー」が新たな産業革命を起こす日本人の自然観を活かす時が来た
想像力が広がります! 環境、エコ関連の本を読むと、「これダメ」「あれもダメ」と言われているようで淋しい気持ちになるのですが、この本はわくわくさせてくれる一冊です!エコに関心がない人にもおススメ。とっても楽しく読めます。水がいらないお風呂、ぜひ入ってみたい!我慢のエコ生活ではなく、こんな素敵で想像力豊かなエコ生活が広がっていくといいですね。
5つ星のうち 2.0 アヤシげな大学教授の本 前著「自然に学ぶ粋なテクノロジー」と重複する話題が多いが、この本はQ&A形式でより情報量を薄くし、幅広い年齢層向けの内容である。
気になったのは、まず彼が工学博士号をもつ研究者兼大学教授でもあるにも関わらず、科学的に疑問のある話題をいくつも持ち出している点だ。
例えば、「シマウマは体の白黒模様で対流が起こり、体温を保つ」というのは、わずかに対流は起こるのかもしれないが、体温までこれで保てるのか疑問。ましてや白黒の壁を作ることで生活空間の温度を一定に保つことなど現実的とは思えない。白黒ストライプによる体温調節説は、既に否定的な見解の論文も挙げられている(Roxton, 2002)。
5つ星のうち 5.0 想像力が広がります!, 2010/4/8
レビュー対象商品: 地球が教える奇跡の技術 (単行本(ソフトカバー))
環境、エコ関連の本を読むと、「これダメ」「あれもダメ」と言われているようで淋しい気持ちになるのですが、この本はわくわくさせてくれる一冊です!エコに関心がない人にもおススメ。とっても楽しく読めます。水がいらないお風呂、ぜひ入ってみたい!我慢のエコ生活ではなく、こんな素敵で想像力豊かなエコ生活が広がっていくといいですね。
5つ星のうち 5.0 Q&Aが読みやすい, 2010/4/8
レビュー対象商品: 地球が教える奇跡の技術 (単行本(ソフトカバー))
先ず松本零士さんが表紙を描いているのにびっくりしました。環境問題に関する素朴な疑問や、聞いたことのなかったけど、タイトル通り地球/自然から学ぶ「ネイチャー・テクノロジー」について等、とても分かりやすく書いていました。Q&A式になっているので、自分が興味がある質問だけも読めるし、全体を通して読んでも、すんなり入ってきました。最後の「八景島コミューン」は、想像したことのない世界でおもしろく、これからのライフスタイルについて考えさせられました。
5つ星のうち 5.0 我慢ではないエコ, 2010/4/8
レビュー対象商品: 地球が教える奇跡の技術 (単行本(ソフトカバー))
これまでに読んだ環境の本は、荒んだ暗い未来と人類の環境負荷の大きさばかりを取り上げており、後ろめたさを駆り立て我慢・節約やエコ商品の購入を促すものがほとんどであった。しかし、この本では、環境問題の解決は我慢やエコ商品の購入ではなく、ライフスタイルを変える必要性があるということをわかりやすく説明している。しかも、そのライフスタイルはひもじい生活ではなく、楽しく心豊かな生活であり、将来に希望と興奮さえ感じることができた。メーカーなどの企業は、是非この本を読み、わくわくする生活を実現可能にするネイチャーテクノロジーを学んでほしい。
5つ星のうち 5.0 レトロ爺さん, 2010/4/6
レビュー対象商品: 地球が教える奇跡の技術 (単行本(ソフトカバー))
メディアや多くの情報にある地球環境問題というものに何となく不安感や後ろめたさのようなものを感じていたが、この本を読ませていただき、眼から鱗の剥がれる気がした。地球環境問題を正面から見つめるということはどういうことなのか、何故そのような問題が起こったのか、この本ほど明解に解説してあるものを見たことがない。そして、その問題を解決する糸口が自然にあるという、そのわくわくするような多くのネイチャーテクノロジーの世界。自分の子供に、やっと地球環境のこと、子供たちに託すべきことが話せる素晴らしいきっかけとなった。
5つ星のうち 5.0 環境制約の中のポジティブな未来像, 2010/3/31
レビュー対象商品: 地球が教える奇跡の技術 (単行本(ソフトカバー))
環境問題とは何かについてわかりやすく書かれた本。環境問題はネガティブに考えがちであるが、ポジティブな未来像が説得力を持って描かれている。環境制約のかかる世界は暗い世界とは限らない。明るい世界が広がる予感を感じさせる。かけがえのない自然と共に生きよう、というメッセージは、当然のことであるが、はっとさせる新鮮な言葉が妙にふに落ちる。表紙に描かれた「地球」は、将来の人類の生存する自然があふれた地球だろうか。意味深い表紙である。
5つ星のうち 5.0 環境問題を前向きにとらえたい人の必読書!, 2010/4/2
レビュー対象商品: 地球が教える奇跡の技術 (単行本(ソフトカバー))
環境問題の深刻さを訴え、危機感を煽るだけの環境本が多い中、本書を読むと環境問題を前向きに捉えることができ、将来に対してワクワクした気持ちになれる。文化や歴史、日本人論、技術などなど、今まで個別に議論されて分断されていたテーマが、”環境”という切り口で融合されているのがとても新鮮である。
5つ星のうち 4.0 豊かに暮らすためにぜひ読んでもらいたい本,
レビュー対象商品: 地球が教える奇跡の技術 (単行本(ソフトカバー))
私たちが普段素朴に思っている疑問を102のQ&A方式で書かれているので、最初から読まなくとも興味のあるところからよめる。
若者向けに書かれた本のようだ。生き物が教えてくれるネイチャーテクノロジーの実例から、本当の環境問題について。さまざまな視点から述べている。
現状を変えるには、今までのライフスタイルを変え、賢い消費者になる。「足るを知る」それが私たち一人一人が明日からでもできることかなとも思える松本零士氏が描かれた表紙、関心のない方でも思わず手にとって読みたくなるような本である
5つ星のうち 5.0 自然の知恵をエコに, 2010/4/12
レビュー対象商品: 地球が教える奇跡の技術 (単行本(ソフトカバー))
前半は「カツツムリの殻から汚れないタイルを作る」「トンボの羽で電気を起こす」等環境に負荷の少ない驚きのネーチャー・テクノロジー(生物模倣技術)をその思想とともに紹介。後半はいわゆる環境問題を扱っていますが「地球温暖化問題」を声だかに主張するわけではなく将来的には必ず来るであろう「資源・エネルギーの枯渇」の観点から環境技術を考えます。
科学技術・環境問題についての押しつけがましさは全くなく不思議なほど心穏やかになる良著です。
5つ星のうち 2.0 アヤシげな大学教授の本, 2010/5/7
レビュー対象商品: 地球が教える奇跡の技術 (単行本(ソフトカバー))
前著「自然に学ぶ粋なテクノロジー」と重複する話題が多いが、この本はQ&A形式でより情報量を薄くし、幅広い年齢層向けの内容である。
気になったのは、まず彼が工学博士号をもつ研究者兼大学教授でもあるにも関わらず、科学的に疑問のある話題をいくつも持ち出している点だ。
例えば、「シマウマは体の白黒模様で対流が起こり、体温を保つ」というのは、わずかに対流は起こるのかもしれないが、体温までこれで保てるのか疑問。ましてや白黒の壁を作ることで生活空間の温度を一定に保つことなど現実的とは思えない。白黒ストライプによる体温調節説は、既に否定的な見解の論文も挙げられている(Roxton, 2002)。
科学者としてこのような話題を紹介するのはいかがなものか。他にもカーボンフットプリントを用いたやや乱暴な考察も行っており、環境問題の本質を見誤らせる危険性がある。
自然に学ぶ姿勢を著者は「ネイチャーテクノロジー」と呼んでいるが、そもそも科学というのは自然から秩序を学び、そのメカニズム・法則性を記述していくものであり、何ら新しいことを言っているわけではない。
科学技術は今も昔も生き物や自然の力を借りることを前提にして利用されている。例えば我々は微生物のタンパク質生産メカニズムを明らかにすることでインターフェロンを作らせているし、植物や動物の生理機能を知ることでいつでもおいしい肉や野菜を食べることができている。
これも著者の言葉を借りれば「自然のすごさを人間の知恵でリ・デザインし直す」ことだと私は思うが、著者はこのような重要なイノベーションは取り上げず、人目を引きやすいシマウマの体色とかカタツムリの構造とかいわゆる「キワモノ」を取り上げて重要だという。
環境問題の本質は、地球に存在するあらゆるエネルギーやマテリアルの供給量や循環時間を考えながら生きていく必要があるということである。著者の紹介するキワモノ的なネタはこの本質から明らかにずれている。
5つ星のうち 3.0 受験生募集の?, 2010/5/15
レビュー対象商品: 地球が教える奇跡の技術 (単行本(ソフトカバー))
理系離れが進んでいるので、受験生確保のために高校生向けに書かれた本のようである。平易な文章で一般人にも読みやすい。
しかし、「ものを基準としない経済」や「敗者を作らない」など、社会科学の面から見るとかなりいい加減な事が書かれている。これでは、社会学や経済学への偏見を作ることにつながりかねない。趣旨としては悪くないのだが、余計なことを書いて混乱させるので大幅に減点した。
23:25 2014/03/20


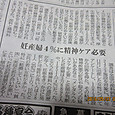

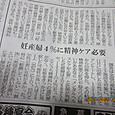



コメント