日本軍と日本兵 米軍報告書は語る
引用
日本軍と日本兵 米軍報告書は語る (講談社現代新書) [Kindle版]一ノ瀬俊也 (著)
容紹介
日本軍というと、空疎な精神論ばかりを振り回したり、兵士たちを「玉砕」させた組織というイメージがあります。しかし日本軍=玉砕というイメージにとらわれると、なぜ戦争があれだけ長引いたのかという問いへの答えはむしろ見えづらくなってしまうおそれがあります。本書は、戦争のもう一方の当事者である米軍が軍内部で出していた広報誌を用いて、彼らが日本軍、そして日本人をどうとらえていたかを探ります。(講談社現代新書)
内容(「BOOK」データベースより)
「規律は良好」「準備された防御体制下では死ぬまで戦う」「射撃下手」「予想外の事態が起きるとパニックに」敵という“鏡”に映しだされた赤裸々な真実。
フォーマット: Kindle版ファイルサイズ: 4157 KB紙の本の長さ: 179 ページ
出版社: 講談社 (2014/2/28)販売: 株式会社 講談社
狂信愚行でも愛国勇気でもない 悲しい合理的判断の日本兵, 2014/2/6
INAVI (日本国、東京) - レビューをすべて見る(トップ500レビュアー) (VINEメンバー)
レビュー対象商品: 日本軍と日本兵 米軍報告書は語る (講談社現代新書) (新書)
本書は、米軍資料を中心に戦後の日本人戦史家の批評も織り込み、対米戦争における日本軍・日本兵の戦い方(主に陸軍の太平洋諸島での戦闘)を明らかにすることで、日本軍・日本兵の本質に迫った一冊。
他著でも同様のアプローチであるが、著者は政治や思想信条を前提にした考察を排除すること、主観的な資料・証言に依拠することなく客観的つまり米軍側の公的資料を拠り所に、論証を進めている。
もともと公式資料に乏しく、また、今となっては当事者の証言も得難い現在において、日本軍・日本兵というか日本の戦争を論じる本の多くが、マクロというかあの戦争は悪であるという価値観を前提に全てを否定する見方、それと、ミクロに個々の兵士や将校の愛国心や善行を拠り所に個々の戦闘や戦争全体を肯定していく見方の何れかに立ちがちであり、互いに交わるべくもなく、読者もいずれかの立場に寄った形が大勢と思われる。
そうした前提においては、南方で玉砕を続けた日本軍・日本兵は、愚かな指導者に狂気の沙汰の死を強要される悲劇の犠牲者か、愛国の心を以って勇猛果敢に闘い抜いた美しきヒーローのいずれかになるしかない。
しかしそうではない!著者は静かにしかし強く論証している。物量・武装で圧倒される中で、次第に奇襲から防御戦へまた銃剣から機関銃更には戦車砲・戦車へと戦闘を近代的に改善する日本軍の試みがあったこと。しかし、全てを冷静に分析する米軍の一層の強力な軍事力を前に、死を前提としたタコツボ死守か戦車への肉弾攻撃を「合理的」に選択するしか日本軍には術がなかったこと。この論理的な分析は、多くの読者に目から鱗となろう。また、栗林中将だけを突出したヒーローと考えない発想や日本兵の中にも様々な内心・言動があったことなど、著者だからこその鋭い考察もポイントが高い。
戦後生まれ平和育ちの私は、死を前提とした戦闘を決して「合理的」には考えることが出来ない。
しかし、私達の先祖が選んだその選択は、決して狂気だけでも愛国だけでもないことが、本書からは見えてくる。
悲しいとしか言いようのない選択をせざるを得なかった日本軍・日本兵は、決して過去の切り離された存在ではなく、血縁を以って私達につながる時代の違うだけの私達であるのだから、私達は現在において「合理的」に何を為し何を為すべきでないのかを考えるべきで、その点で本書は多くのことを私達に教えてくれていると思う。
最後になるが、臨機応変の一言で現場任せにして戦略・戦術を考えない上層部とか、計画を最後までやり抜かず自暴自棄になる現場とか、一旦プランが崩壊すると一気に逃げ出すとか、戦場以外でもこうした特性が日本人にはあるという点は、非常に興味深いところであった。こうした偏見やステロな見方に終始せず、汝が敵を知れという孫子の兵法に通じるアプローチを米軍が心がけたことも、著者はじめ近年の若手の作品に多く見られる指摘であるが、これもまた現代に通じる見識と評価したい。
5つ星のうち 4.0 大本営参謀の「合理性」の偏狭さ, 2014/3/10
レビュー対象商品: 日本軍と日本兵 米軍報告書は語る (講談社現代新書) (新書)
米軍は大戦中、日独軍の行動を分析した報告書を月刊で発行し、各部隊に配布していたという。本書は、その報告書を通し世界最強組織、米軍が太平洋戦争を通じて見た日本軍と日本兵の行動分析を紹介している。
前半は日本兵の行動を解説している。「つかみ」の日本兵と中国兵の判別法の話が面白い。「LとRの発音で見分けよ。日本兵はLの発音が苦手だ」という。昔からダメなのか。また、医療や糧食、社会生活も詳しく書いている。「海草、干し魚は口に合わないが、食糧不足時は食べることもあり」とか。また日本兵捕虜への厚遇が実に理にかなっている。「『捕まれば米兵に殺される』と思い込んでいるので、厚遇すれば、恩義に感じ情報を与えようとする」「貸し借りに生真面目だから恩を着せよ」。少なくない米兵が日本兵を殺していたが、「日本兵を助命すれば、米兵の命も救われる」と。戦艦大和や零戦のスペックも捕虜から得ていた。好意ではなく心理分析に基づくメリットから助命していた。
後半は日本軍部隊が陸上でどのように戦ったかを見る。前中期は、夜間・奇襲攻撃に固執していた。戦車には近接攻撃以外の対抗策がなかったため、20メートルまで接近しての肉迫攻撃、最後は穴から飛び出す人間地雷まで登場する。また、上陸作戦が最大の問題になるにつれ、日本側による上陸阻止戦術が課題になった。固い岩盤に地下トンネルを掘りめぐらし、近寄ってきた米兵に機関銃で狙い撃ちするため、撃退に手を焼いた。敗色濃厚になるにつれ、日本軍の目的は、撃退するより、米軍に出血を強要し、厭戦気分にさせ有利な和平に持ち込むことに主眼が置かれるようになった。日本軍の戦術は非合理のように見えるが、大本営参謀たちが考えるこのような偏狭な合理性に基づいている。また、硫黄島などを除き、最後まで水際殲滅にこだわったため、予測はつきやすかった。ともかく、死を顧みない持久防御戦術は、米軍にとって脅威であり続けた。
自分の癖を自身であまり認識しないのと同様、日本軍・兵も自身の癖や深層心理を自分では気づきにくいが、米軍は多くを見抜いていた。「射撃が下手」など冷静な比較も敵軍アメリカだから見える。日本軍という繰り返し論じられてきたテーマではあるが、多くは日本側の資料であり本書で初めて知ったことも多い。本書は新たな視点を提供している。
5つ星のうち 5.0 旧日本軍は軍事的合理性を欠いていたわけではない。しかし...,
レビュー対象商品: 日本軍と日本兵 米軍報告書は語る (講談社現代新書) (新書)
松代大本営跡を訪れたことがある。空襲が激しくなった昭和19年、旧日本軍が首都機能移転のために長野県松代の山中に掘った、延べ10,000mにも及ぶ巨大地下壕である。現在公開されているのは、そのごく一部、500m程度に過ぎないが、そこを歩いただけで日本陸軍が本気で本土決戦に備えていたことが、問答無用の迫真性をもって理解できる。本気でなければ、こんなとんでもないものを作れるはずがない。
本書を読むと、なぜ帝国陸軍が松代山中にこれほど膨大なトンネルを掘ったのかが、実に良く分かる。戦争のほとんどの期間、火力と機動力において圧倒的に優勢であった米軍に対して、最も効果的だった戦術が、「穴に立て篭もる」ことだったのである。
だが、モグラのような地下陣地に立て篭もる作戦には、勝利への展望も和平への希望もなかった。単に「負けるのを遅くする」戦術に過ぎないにもかかわらず、それしか縋るものがなかったという意味において、松代大本営は「合理性を仮装した狂気」と言わざるを得ない。
本書は、米軍資料という他者の目を通じて、 合理性をまとった狂気へと落ちていく日本軍の姿が活写されている。一読の価値ありである。
5つ星のうち 5.0 日本側からの視点では、なかなか見えなかった実態, 2014/2/10
レビュー対象商品: 日本軍と日本兵 米軍報告書は語る (講談社現代新書) (新書)
従来の日本側からの資料や証言では解らない(あるいは敢えて語られなかった?)、々な日本兵・日本陸軍の姿が、米軍の記録から浮かび上がっています。そこからなされた著者の考察も、非常に興味深いものでした。
また、特定のイデオロギーに好都合な事実を選別して取り上げる様な事をせず、冷静に、長所も短所も記されていると感じられ、その点も非常に好感がもてます
是非、ドイツ陸軍編も執筆していただきたいです。もしそうされたなら、今度は自分で日本陸軍との比較・考察をしてみたいと思っています。
5つ星のうち 5.0 兵士の悲しみが見える, 2014/2/17
レビュー対象商品: 日本軍と日本兵 米軍報告書は語る (講談社現代新書) (新書)
太平洋戦争時の米軍による日本軍についての分析報告書を読み解きながら、当時の日本軍の戦術や行動様式を浮き上がらせる。筆者は、従来のように「ファナティック(狂信的)」な連中として描かれてきた、日本軍についての理解の在り方に疑問を投げかけ、彼らの行動が、ある種の(非常に狭量な)合理性に基づいていた、と結論づけた。
本書を読めば、各地で日本軍がどのように戦ったのかが、とてもリアルに理解できる。難解な専門用語もあり、やや硬質な文章ながら、退路を断たれた兵士の悲しみがそこに見えるし、命を賭した息づかいまで聞こえてきそうなのが、本書のえもいえぬ不思議な魅力だろう。
現代日本人は、右翼(あるいは左翼も)か研究者でないかぎり、日本陸海軍が各地でどのように戦ったのか知らない。師団名や将校の名前はおろか、各地で取られた戦術、具体的な帰結についても知らずに済んできた。だが百田某の手による「永遠のゼロ」といった、甘美で独善的な戦争史観に陥らぬためにも、わたしたちは、先輩たちの足跡を具体的かつ批判的にたどる必要があるし、そうせねば、平和を自らの手で築いていくことなど、できはしないだろう。
5つ星のうち 5.0 米軍が分析した日本軍と日本兵, 2014/3/15
レビュー対象商品: 日本軍と日本兵 米軍報告書は語る (講談社現代新書) (新書)
米陸軍軍事情報部が1942年から1946年までに出版した戦訓広報誌(IB:Intelligence Bulletin)に書かれている内容を中心に、米陸軍が分析した日本軍、日本兵及びのその戦い方について解説したものである。適時、関係する日本側の本や資料も参照されている。
興味深い指摘が多く集められている。従来の日本軍に対する概念をリアルに裏打ちしているものが数多くある一方で、ステレオ・タイプ的なイメージとは違う視点を提供しているものも結構あるし、「日本軍兵士最大の弱点は、予期せざる事態にうまく対処できないことだ。...(中略)...この生来の弱点は、自由な思考や個人の自発性を厳しく退け管理されてきた人生と、少なくとも部分的には関係がある。この弱点は攻撃でも防御でもはっきり表れている」(IB1943年5月号より)のように、かなり突っ込んだ分析をしているものもある。
米陸軍のみた日本兵の全体的な長所と短所については次のように紹介されている。まず長所については、「肉体的には頑健である、準備された防御では死ぬまで戦う、特に戦友が周囲にいたり、地の利を得ている時には大胆かつ勇敢である。適切な訓練のおかげでジャングルは家のようである、規律(とくに射撃規律)はおおむね良好である」とあり、その反対に短所については、「予想していないことに直面するとパニックに陥る、戦闘のあいだ常に決然としているわけではない、多くは射撃が下手、時に自分で物を考えず『自分で』となると何も考えられなくなる」という。
日本軍の戦い方としては、「白兵主義」という言葉に代表される銃剣突撃による肉弾戦がある。しかし、米軍が銃床打撃も使った剣術をトレーニングされていたのに比べて日本兵は突き一辺倒であった上、体格でも大きな差があったことで、防御をかいくぐって白兵戦となった場合でも日本兵の方が優位だとは受け止められていなかったようである。その一方で潜んで至近距離に引きつけてから浴びせる軽機関銃の攻撃は米軍にとって脅威だった。厚遇された捕虜がさまざまな情報をもたらしたことや、遺された日記の解読から前線の将兵たちの士気の低下や不安、あるいは補給が途絶えた日本側の過酷な状況についても伝えられている。
日本軍が様々な戦いから学んで途中で戦術を変化させていったことについては米軍側も察知しており、前線部隊への情報提供としての記述が数多く引用されている。硫黄島の戦いで有名になった洞窟を張り巡らされた陣地の有効性は比較的早くから日本側で認識されていたことがうかがえるし、大戦の後半においては物量で米軍に及ばないとはいえ火力はそれまでより強化され、単体ではなく砲列を用いた集中支援射撃も行われるようになる。水際戦術を放棄して辛抱強く空襲と砲撃に耐えて戦力を温存してから有効射程域に敵を引き込んで一斉射撃を浴びせ、トンネルの奥深くに軍需物資を貯蔵し、バンザイ突撃を控えて持久戦を挑んで粘り強く戦う。防御線の連携を保ち、要塞正面の死角を洞窟間の相互支援で解消するといったことも巧に行われていたことがわかる。
大きな脅威であった米軍戦車に対する日本軍の肉弾攻撃については、グループを作って役割分担を決めて組織的に行われていたことが詳しく示されている。沖縄戦での人間地雷も悲惨である。しかし、物量に圧倒的に劣る日本側にとって、それらの方策は精神主義という一言では片付けられない、それ以外に策のない精一杯の戦い方であったという点で一定の合理性を有していた側面があったこともわかる。
実際に戦った敵であるアメリカ軍から日本軍や日本兵がどのように見えていたのかをたどれる。なかなか読みごたえのある一冊だった。
5つ星のうち 4.0 人命を鴻毛の軽きに比す悲惨。, 2014/1/26
レビュー対象商品: 日本軍と日本兵 米軍報告書は語る (講談社現代新書) (新書)
皇軍の戦いを米軍の視点から見つめ直した作品。永遠のゼロで飛行機のほうは注目が当たっているが、陸でも対戦車人間地雷原として肉攻兵が同様の悲惨が繰り返さていた。これは今でもテロリストの兵器として使われている。大本営のお偉いさんは兵隊の死を鴻毛の軽きに比すと言うくらいなので、こうなるのであろう。塩野七海さんによるとローマ兵と蛮族の最たる違いは人命の重さの違いにあったようだが、それからすると大日本帝国はアジア的な野蛮な精神を継承した国に見えてくる。されば、天皇の名誉を汚す敗戦が遅れて大量に無駄な人命の喪失をきたしたことにも合点がいく。あとがきにあるように蛮族からローマ帝国を継承したドイツ人の敗走の状況がどうであったのか、気になってきます。自作に期待をこめて4星としました。
8:21 2014/03/21


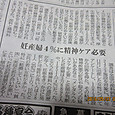

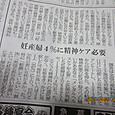



コメント